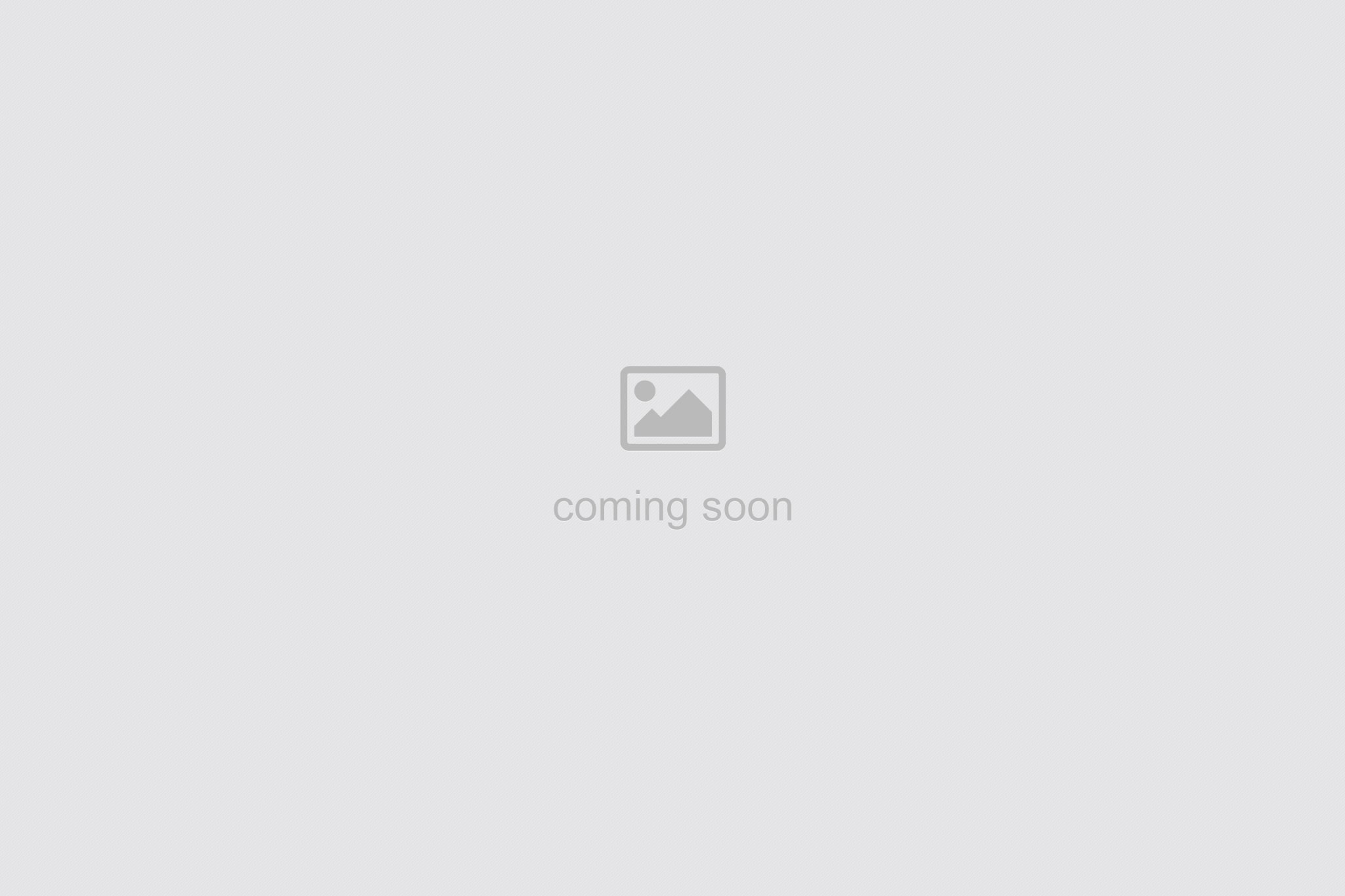生産性を上げるために
近年、生産性という言葉をこれまで以上によく耳にするようになりました。
人口減少や深刻化したり働き方改革が進行する中で、
企業にとって生産性向上は喫緊の課題となっています。
今回は、生産性を上げるために何ができるかをまとめたいと思います。
生産性向上のための取り組み
非生産部門の生産性向上に焦点を当て、以下の3つの取り組みが考えられます。
- 組織全体における生産性向上の仕組づくり: 組織全体で無駄な作業を省き、時間の効率的な活用を促す仕組みを作ります。事務部門のサポートが不可欠です。
- 業務フローの改善: 定型業務を中心に、個々の業務フローを見直し、費用対効果の高いシステムや仕組みを導入して効率化を図ります。
- 各個人の意識改善: 各個人に生産性向上の重要性を認識させ、日々の業務の中で無駄な作業の排除 and 時間の効率的な活用を促します。
中小企業におけるアウトソーシングの活用
中小企業にとって、アウトソーシングはコスト削減だけでなく、 コア業務(本業)への経営資源の集中 という点で大きな効果を発揮します。限られた経営資源を有効活用するためには、既存業務を洗い出し、本業・重点戦略に必要な業務かどうかを見極めることが重要です。コア業務以外はアウトソーシングすることで、時間と人を本業に集中させることができます。
営業・接客のレベルアップ
生産性向上には、営業や接客のレベルアップも欠かせません。
営業・接客は、以下の3段階に分けられます。
- 御用聞き: お客様からの用事を聞き、受注する
- 提案型: 顧客のニーズを捉え、商品を提案する
- ソリューション型: 顧客の課題を解決するための提案を行う
最終的には、顧客の課題解決に貢献できる ソリューション型 の営業・接客を目指しましょう。
採算性の重要性
生産性と同様に、 採算性 も重要な要素です。採算度外視の活動は、戦略に沿っているか、一貫性があるかを見極める必要があります。採算性を見極め、資源を集中投下できるよう努力することが大切です。
ピーター・ドラッカーの問い
経営学者ピーター・ドラッカーは、
生産性向上のためには以下の3つの質問を問うべきだと述べています。
- 何が目的か?
- 何を実現しようとしているか?
- なぜそれを行うのか?
これらの質問は、自身の仕事の本質を見つめ直すきっかけを与えてくれます。
まとめ
生産性と採算性を向上させるためには、
組織全体の仕組みづくり、業務フローの改善、
個人の意識改革、そして営業・接客のレベルアップが重要です。
本業に集中し、顧客の課題解決に貢献できるよう、常に改善を心がけることが大切かと思います。
ブログ名「おふくわけ」について
【感謝】請求書の電子化にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます!

「電子化に切り替えます!」
と発表した当初は、正直なところ不安でいっぱいでした。
「やっぱり紙の請求書じゃないとダメ」
というお客様が多いんじゃないか・・・
「電子化なんて面倒だ」
と思われるお客様もいるかもしれない・・・
そんなことを考えると、ドキドキものでした。
しかし、ふたを開けてみれば、ほとんどのお客様が電子化に快く同意してくださったのです!
本当にありがたい限りです!!
もちろん、中には「やっぱり紙で送ってほしい」というお客様もいらっしゃいます。
そのようなお客様には、引き続き紙の請求書をお送りしておりますのでご安心ください。
実は、電子化に切り替える前に、お客様にアンケートを実施させていただきました。
その結果が、予想以上に好意的な意見が多かったのです。
「早く電子化してほしい」
「請求書をデータで管理できるのは助かる」
「ペーパーレス化に貢献できるのは嬉しい」
などなど、たくさんの温かいお言葉をいただきました。
中には、
「請求書はいつもファイルにまとめて保管しているけど、電子データだと検索が楽になるから助かる」
という、具体的なメリットを挙げてくださる方もいらっしゃいました。
時代はどんどん変わっている
今回の請求書電子化を通して、時代の変化を改めて実感しました。
少し前までは、「請求書は紙で送るのが当たり前」という認識が一般的でした。
しかし、今では「請求書はデータで受け取るのが当たり前」になりつつあります。
もちろん、紙の請求書には紙の請求書の良さがあると思います。
しかし、デジタル化によって効率化できることはたくさんあります。
請求書に限らず、
最近、巷で騒がれているAIも個人的に利用していますが、その進化には目を見張るものがあります。
1年の間でもどんどん進化をしていることは驚異的です。
AIが私たちの生活や仕事を大きく変える日は、そう遠くないかもしれません。
デジタルとアナログの使い分けが重要
もちろん、デジタル化すればすべてが解決するわけではありません。
アナログな部分も大切にする必要があります。
デジタルとアナログをバランス良く使い分けることが、
弊社も、デジタルとアナログの良いところを組み合わせながら、
今後とも、よろしくお願いいたします。